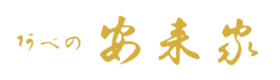二月中旬、初釜と節分を越えて——日々の仕込みの解像度
新年を迎えてから、気づけば二月も中旬になりました。
店の中の空気も、朝の水の冷たさも、正月の張りつめた気配から、冬の静けさへと少しずつ移っています。
私たちにとってこの時期は、行事の料理と普段の献立が並走し、仕込みの段取りがいっそう緻密になる季節でもあります。

一月はじめは、各地で茶懐石の初釜が催されます。初釜の席では、流れそのものが「おもてなし」の骨格になります。
下ごしらえの精度を揃え、手順を整えて臨みました。
茶の湯の席の料理は、華やかさよりも、ほどよく抑えた輪郭が求められます。
出汁の立ち上がりを強くしすぎず、余韻を濁らせず、器の中に季節を静かに置く。その基本に立ち返る一月でした。

続いて節分。毎年恒例の恵方巻。巻寿司は単純に見えて、ごまかしが利きません。
ご飯の固さ、酢の入り方、具の温度差、切り口の整い。どれかひとつが外れると、食べたときの一体感が崩れます。今年は、巻や上巻に加えて海鮮巻もきちんと数を揃えました。いろんな巻寿司を楽しんでもらえていたら嬉しいです。
大量に巻く日ほど、一本ごとの“同じ美味しさ”を守ることが、そのまま誠実さになると感じています。仕出し料理として、日々の仕事の延長だと思います。

そして節分のあと、今年最初の生國魂神社での茶懐石出張料理が続きました。
昨年(二〇二五年)は四回担当させていただき、今年も与えられた担当月に向き合います。
比べるものではありませんが、その都度、その日の最高を目指したいと思います。
場が変われば火の入り方も変わり、器が変われば盛りの線も変わります。
だからこそ、段取りを固めながらも、最後はその日の湿度、温度、手の感触に耳を澄ませて、料理を決めていきます。
ここまで挙げた三つは、いずれも分かりやすい“節目”です。
けれど、安来家の日々は、やはり通常営業の積み重ねで成り立っています。
阿倍野でお席を整え、懐石・会席の流れを組み立て、季節の移ろいを一皿ずつに落とし込む、あるいは、仕出しのご注文をいただき、配達の箱の中に店の時間を詰める。
その繰り返しがあるからこそ、大きな行事の料理も、地に足のついたものになります。
日本料理は、とかく“晴れの日”の印象を持たれがちですが、むしろ「普段の精度」が味を決めると考えています。
最近、仕込みをしていてふと感じるのは、行事の料理には「型」があり、その型が味方になるということです。
大量調理は、一つの小さな乱れが全体の崩れに繋がります。
だから、型は守る。
けれど同時に、日々料理と向き合う人間として、型の内側で“もっと良くできる点”を探します。
ほんのわずかな改善が、何年も積み重なると、ある日突然、大きな発見に繋がることがあります。
近頃は、その「解像度」が少し上がってきた感覚があります。
普段の懐石料理はもちろん、同じものを数多く仕上げる場面でさえ、ただ“整える”から一歩進んで、“心が動く地点”へ近づけるのではないか、と。
たとえば冬の会席では、温かい椀の立ち上がりに、冷えた空気の輪郭が重なって見える瞬間があります。二月の懐石では、芽吹きの気配がまだ遠い分、食べ終えた後に残る余韻を澄ませたくなる。そうした季節の読み取りは、派手な演出ではなく、日々の小さな手入れから生まれるものだと感じています。
行事がひと段落すると、また普段の献立により身が入る感覚があります。器を選び、出汁を引き、同じ動作を繰り返しながらも小さな改善を加えながら少しずつ季節を更新していく。
いつの季節にお越しいただいても、その季節をきちんと味わっていただけるように。